
「喉に常に何かが垂れている感じがする」
「咳が長引く」
「夜ぐっすり眠れない」
これらの症状は、後鼻漏(こうびろう)によるものかもしれません。
後鼻漏とは、鼻水が鼻から喉に流れ落ちる状態を指し、違和感や咳、不眠、集中力低下などさまざまな不調を引き起こします。
西洋医学では「鼻の病気」と捉えられることが多いですが、東洋医学の視点から見ると、後鼻漏は全身のバランスの乱れと深く関わっているのです。
後鼻漏とは? 東洋医学からの捉え方
鼻水は本来、誰にでも毎日1〜1.5ℓほど分泌され、自然に喉へ流れています。
しかし後鼻漏では、その量・質・流れる速さに異常が起こり、痰の絡みや咳、口呼吸、不眠といった不快な症状へとつながります。
「鼻だけの問題」と思って鼻炎治療をしても根本改善しないのは、体質や生活習慣の乱れが根底にあるからです。
東洋医学では後鼻漏を、体質を3つのパターンに分けて考えます。
後鼻漏を引き起こす3つの体質タイプ
1. 水分過多タイプ(痰湿)
特徴:むくみ、頭重感、倦怠感、胃腸の弱り。舌に歯型が出やすい。
原因:水分代謝がうまくいかず、余分な水分が体に停滞。
対策:
- 有酸素運動やウォーキングで汗をかく
- 食材:ハト麦、豆類、生姜、シソ
- ツボ:陰陵泉、水分へのお灸
- 注意点:冷たい飲み物や水の過剰摂取は避ける
2. 巡りが悪いタイプ(瘀血)
特徴:首肩こり、冷え、便秘、爪の色が悪い。デスクワークに多い。
原因:血流の停滞で老廃物が処理されにくくなる。
対策:
- ストレッチや軽い運動で血流を促す
- 食材:青魚、納豆、酢の物など活血作用のあるもの
- ツボ:三陰交、血海を温める
3. 熱こもりタイプ(熱邪)
特徴:口臭、頭痛、目の充血、鼻炎、逆流性食道炎などを併発。
原因:辛い物・甘い物・脂っこい食事、睡眠不足やストレスで体に熱がこもる。
対策:
- 熱を冷ます野菜(ゴーヤ、ナス、春菊、豆腐)を加熱調理して摂取
- ツボ:照海、尺沢へのお灸
- 睡眠リズムを整え、ストレスケアを心がける
※実際には、複数の体質が重なっている方も多いです。
後鼻漏を悪化させる生活習慣
食生活の乱れ
油っこい料理や甘い物、味の濃い食事は東洋医学で「膏梁厚味」と呼ばれ、炎症や熱を助長します。さらに辛い物やアルコールも要注意。
👉 対策は「まごわやさしい(豆・ごま・わかめ・野菜・魚・しいたけ・芋)」を意識した食事です。
浅い呼吸
呼吸が浅い方は肺や呼吸器系が弱く、鼻・喉のトラブルを抱えやすい傾向があります。
👉 腹式呼吸や腹筋を鍛えることで肺機能を高めると改善が期待できます。
体の緊張
肩や首のこわばりは血流を悪くし、炎症が鎮まりにくくなります。特に「胸鎖乳突筋」が硬くなると後鼻漏の悪化要因に。
👉 首のストレッチや耳の後ろのツボ押し、入浴で緊張を解消するのが効果的です。
鍼灸による後鼻漏改善アプローチ
東洋医学の鍼灸は、症状だけにアプローチするのではなく、体質そのものを整えて根本改善を目指す施術です。
鍼灸の効果は以下のような点に現れます。
- 鼻や喉周囲の炎症を鎮める
- 自律神経を整え睡眠の質を高める
- 首・肩の緊張を緩めて血流を改善
- 免疫機能を高め、炎症を起こしにくい体質へ導く
実際に当院でも「喉の違和感が減った」「夜眠れるようになった」と喜ばれる方が多く、薬に頼らずに体質改善を目指せる点が鍼灸の魅力です。
まとめ
後鼻漏は「鼻だけの病気」ではなく、食事・呼吸・緊張など生活習慣や体質の影響を強く受けます。薬で一時的に抑えるだけでなく、東洋医学的な体質改善が根本解決につながります。
鍼灸はそのための有効なアプローチであり、後鼻漏に悩む方のQOL(生活の質)を高めることができます。
豊中市で後鼻漏や慢性的な鼻・喉の不調にお悩みの方は、ぜひ一度、東洋医学に基づく当院の鍼灸を体験してみてください。
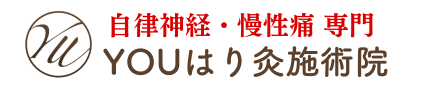
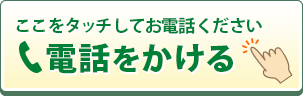
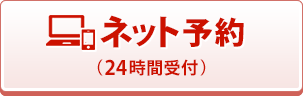







お電話ありがとうございます、
YOUはり灸施術院でございます。