なぜ肩こりは起こるのか?
肩こりは単なる「筋肉の疲れ」ではなく、東洋医学では 気・血の巡りが滞ることで生じる不調 と考えます。
姿勢の悪さや目の酷使、冷え、ストレス、食生活の乱れなど、日常の小さな積み重ねが肩や首に現れてしまうのです。
東洋医学から見た肩こりのタイプ
肩こりの背景には体質や生活習慣が深く関わっています。
代表的なタイプを挙げると次の通りです。
- 筋肉の緊張タイプ:長時間のデスクワーク、スマホ姿勢によるもの。
- ストレスタイプ:精神的な緊張で「肝」の働きが乱れ、気血が滞る。
- 冷えタイプ:冷房や寒さで「風寒邪」が体に入り、肩のこわばりを生む。
- 痰湿タイプ:食生活や水分代謝の乱れで、重だるい肩こりになる。
自分のタイプを知ることが、効果的な養生につながります。
日常でできる肩こり養生法
① 温めて血流を良くする
肩や首を冷やさないことが第一。
入浴や蒸しタオルで温めると血流が促進され、こりが和らぎます。
② 軽い運動・ストレッチ
肩甲骨を大きく回す運動や、背伸びなどの軽いストレッチを日常に取り入れましょう。
長時間のデスクワークでは1時間ごとに体を動かすのが理想です。
③ 食事の工夫
甘いものや脂っこい食事の摂りすぎは「痰湿」を生み、肩の重だるさの原因に。
旬の野菜や温かいスープなど、消化に優しい食事を心がけましょう。
④ ストレスケア
深呼吸や瞑想、趣味の時間を大切にすることで「肝」の働きが安定し、肩こりが和らぎます。
睡眠の質を高めることも重要です。
⑤ ツボ押し

- 肩井(けんせい):肩の真ん中あたり。肩こりの代表的なツボ。
- 合谷(ごうこく):手の甲、人差し指と親指の間。血流を整え、首肩の緊張をやわらげる。
- 風池(ふうち):後頭部の生え際、首のくぼみ。頭痛や眼精疲労にも効果的。
指圧やお灸で刺激するとセルフケアになります。
鍼灸でのサポート
養生法を続けても改善が難しい肩こりには、鍼灸治療が効果的です。
鍼灸では肩だけでなく全身の経絡を整えることで、再発しにくい体質へと導きます。
まとめ|肩こりは日々の養生で予防できる
肩こりは放置すると慢性化し、頭痛や不眠、自律神経の不調にもつながります。
日常の養生を心がけながら、必要に応じて鍼灸を取り入れることで、根本からの改善が期待できます。
「肩こりは体からのサイン」。自分の生活を見直すきっかけにしてみてください。
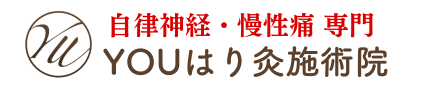
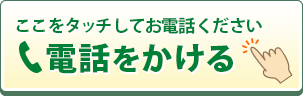
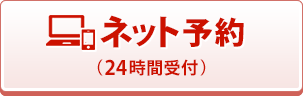







お電話ありがとうございます、
YOUはり灸施術院でございます。